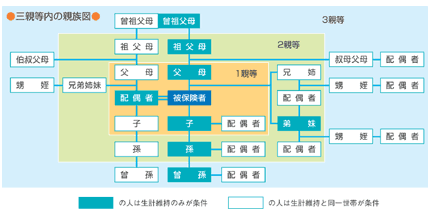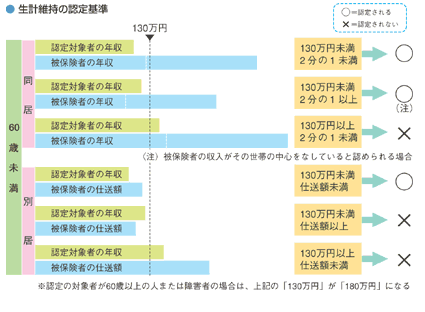|
被扶養者資格の適用の適正化(被扶養者の範囲と認定基準)
|
|||
| 健康保険の被保険者に扶養されている75歳未満の人は、一定の条件に該当すれば被扶養者として認定され、本人が保険料を負担しなくても健康保険の給付が受けられます。 被扶養者として認定されるには、①被保険者とどのような親族関係にあるか、②同一世帯にあるか、③生計維持関係にあるか、④認定対象者の収入がいくらか、などが基準になります。 従業員の家族が被扶養者に該当したときは、事業主が「被扶養者(異動)届」を年金事務所(または健康保険組合)に提出しなければなりません。 また、被扶養者が就職したときや一定の収入を超えたなど、被扶養者の条件に該当しなくなったときも、事業主は「被扶養者(異動)届」を提出(被保険者証を添付)しなければなりません。この届出を行っていないと、協会けんぽにおいてはその被扶養者分の給付も負担することになり、結果として加入者の保険料負担も増えます。 協会けんぽでは、保険料負担の抑制や医療費の適正化を目的に、被扶養者資格の再確認を原則として毎年度実施しています。平成23年度以降の実施にあたっては、平成22年度同様に就職などによる二重加入の早期確認に重点が置かれるようです。 ■被扶養者になれる親族の範囲は 健康保険の被扶養者になるには、「主として被保険者の収入により生計を維持されている三親等内の親族であること」が条件ですが、さらに親族の範囲によっては「同一世帯であること」が条件になります。どちらの場合も75歳の誕生日の前日まで被扶養者となります。75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者になります。 ■被扶養者の認定基準は 被扶養者の対象となる家族に収入がある場合は、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」ことが被扶養者の認定基準となります。 |
|||