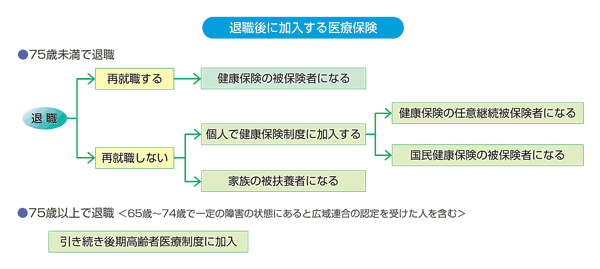
<図をクリックすると拡大されます>
■健康保険の適用事業所に再就職する
退職後に健康保険の適用事業所に再就職する人は、引き続き健康保険に加入することになり、事業主が資格取得と健康保険証の発行の手続きを行います。
70歳未満は健康保険と同時に厚生年金保険にも加入することになるため、事業主に年金手帳を提出します。
○手続き
再就職先の事業主が資格取得日(入社した日)から5日以内に、事業所を管轄する「年金事務所」へ「健康保険被保険者資格取得届」を提出します。被扶養者がいれば「健康保険被扶養者(異動)届」も提出します(健康保険組合の加入事業所の場合は「健康保険組合」へ提出)。
○保険料
保険料は標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を乗じた額で、本人と事業主が折半で負担します。本人が負担する保険料は給与と賞与から事業主が天引きし、保険者へ毎月納付します。
■健康保険の任意継続被保険者になる
会社を退職して健康保険の被保険者資格を喪失したときに、個人の希望により、任意継続被保険者として2年間、健康保険に加入できます。保険料は全額本人負担です。
○任意継続になる条件
任意継続被保険者になる条件は、資格喪失日(退職した日の翌日)までに、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることです。
また、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請しなければなりません。
○申請に必要なもの
申請の手続きは、本人が「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を作成します。申出書は協会けんぽのホームページからダウンロードできます。また、協会けんぽ都道府県支部や年金事務所の健康保険の窓口にも備え付けてあります
被扶養者がいるときは、その旨を申出書に記入します。被扶養者を追加するときは「健康保険任意継続被扶養者(異動)届」を作成して提出します。
申請先は、自宅の住所地を管轄する協会けんぽ都道府県支部です(健康保険組合の加入事業所の場合は「健康保険組合」へ提出)。
<添付書類>
申出書には、被扶養者の年収を記入しますが、続柄に応じて次の書類の添付が必要になります。
(1)被扶養者の年収は、130万円未満(60歳以上は180万円未満)であることが要件。
学生および未就学児を除き、被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入(無収入)が確認できる課税(非課税)証明書などの書類を添付。
(2)被保険者と同居していることが条件である被扶養者(直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の人)の場合は、同居の事実が確認できる住民票などの書類を添付。
○加入期間
加入期間は、任意継続被保険者になった日から2年間です。ただし、以下のように資格喪失に該当する場合を除きます。
○資格喪失
次のいずれかに該当するときは、任意継続被保険者の資格を喪失します。資格を喪失したときは、被保険者証を返納します。
(1)任意継続被保険者になった日から2年が経過したとき
(2)保険料を期限まで納付しなかったとき
(3)就職して健康保険の被保険者になったとき
(4)後期高齢者医療の被保険者になったとき
(5)亡くなったとき
(3)、(4)に該当したときは「任意継続被保険者資格喪失届」の提出が必要です。
○保険料
任意継続被保険者になると、退職前に折半負担だった事業主分も負担することになり、退職前の健康保険料の2倍の額になります。
ただし、保険料の計算の基になる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か28万円(平成24年度)のいずれか低い額にするなど、保険料の上限が定められています。
<前納する場合の保険料>
保険料は、事前に6ヵ月分または12ヵ月分を前納することができます。この場合、保険料が割引になります。
前納の申出は、資格取得申出書の保険料の納付方法欄にチェックして申し出るほか、随時に申出できます。
<納付期限>
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書で、その月の10日(10日が土日祝祭日の場合は翌営業日)までに納付します。納付期限までに保険料を納付しないと、納付期限の翌日で資格喪失になります。
初回の保険料の納付期限は、協会けんぽ支部が指定した日となります。
<保険料の納付場所>
(1)納付書による納付
コンビニエンスストア/金融機関の窓口/銀行などのATM/インターネットバンキング
(2)口座振替による納付
初回分を除き、口座振替の申出書を提出することで、口座振替による納付が可能になります。口座振替開始月は、金融機関と協会けんぽ支部の手続きがすべて完了した月から、毎月1日に引き落としになります。
■家族(健康保険)の被扶養者になる
健康保険の被扶養者になるには、被保険者の三親等内の親族で、被保険者によって生計が維持されていることが条件になります。
○被扶養者になるための条件
<被扶養者の範囲>
(1)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者により生計を維持されている人
(2)被保険者と同一世帯で、主として被保険者の収入より生計を維持されている次の人
(ア)(1)以外の三親等内の親族
(イ)内縁関係にある配偶者の父母および子
(ウ)(イ)の配偶者が亡くなった後における父母および子
<収入がある場合の認定基準>
(1)同居の場合:年収が130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満であること (2)別居の場合:年収が130万円未満で被保険者からの援助額より少ないこと
認定対象者が60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収の認定基準が180万円未満になります。
収入を確認するため、添付書類が必要な場合があります。
○保険料
健康保険制度全体から拠出されるため、被扶養者本人の負担は必要ありません。
○手続き
家族が勤務する会社の事業主が、資格喪失日(退職した日の翌日)から5日以内に、事業所を管轄する「年金事務所」へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します(健康保険組合の加入事業所の場合は「健康保険組合」へ提出)。
■国民健康保険の被保険者になる
「健康保険の被保険者になる」、「健康保険の任意継続被保険者になる」、「家族が加入している健康保険の被扶養者になる」以外の75歳未満の人は国民健康保険に加入しなければなりません。
○保険料
国民健康保険の保険料は保険料方式と税方式があり、各市区町村によって異なります。
○手続き
本人が資格喪失日(退職した日の翌日)から14日以内に、住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口へ「国民健康保険被保険者資格取得届」を提出します。
その際、健康保険の被保険者資格の喪失日や、被扶養者でなくなった日を証明する「健康保険・厚生年金保険資格取得・喪失等確認申請書」の添付が必要になるため、住所地の年金事務所から交付してもらいます。
■75歳以上は後期高齢者医療に加入
75歳以上(または65歳から74歳で一定の障害があることについて広域連合の認定を受けた人)の人は在職時と変わらず、退職後も引き続き後期高齢者医療制度に加入することになります。 退職 退職後に国民健康保険に加入していた人は、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度に加入します。本人の手続きは不要で、自動的に移行になります。75歳になる誕生月の前月中に「後期高齢者医療被保険者証」が送付されてきます。
65歳から74歳で一定の障害がある人は、認定の申請手続きが必要です。
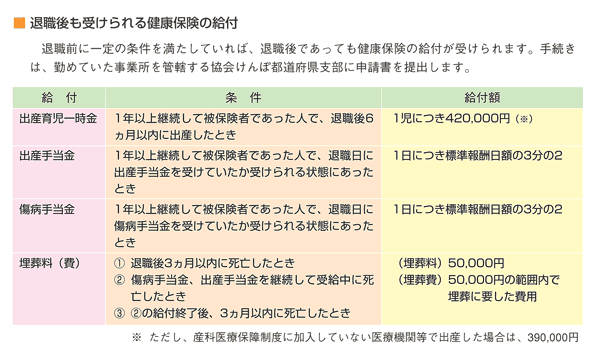
<図をクリックすると拡大されます>
|
